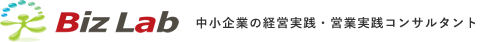スピーカーが話しをしているのに参加者がウツラウツラ、今にも眠ってしまいそうな人までいる会議。
一部の人しか、口を開かない会議。
みなさんの会社の会議、またはセミナーなど、参加者の態度はどうだろうか。
今日のテーマは、「場づくり」だ。
会議やセミナーの場を作っているのは「司会や講師だけにあらず!」
今はまだ科学的に解明されていないが、「場づくり」「場の空気」という言葉がある。
空気といえば、地球上のどこにもあるものだ。
会議室、セミナー会場、それだけでなく、もちろん家の中や電車の中にもある。
さて、話が、会議やセミナーとなると
今いる場、その場所の空気をつくると言う意味での「場づくり」が、司会者やセミナーなどの講師、またファシリテーターには必要とされている。
さて、ではその「場づくり」とはどういうものだろうか。
場の空気とは、その場にいる人の、感情により決まると言われている。
参加者の感情が、自然とその場の空気となって、その空間をつくりあげるのだ。
もちろん、会場の席の配置によって、椅子の向きによって、空調の暑い寒いによって、感情には影響が出るだろう。
これらもファクターであることは間違いない。
そして何より、司会者や演者の話し方は、参加者の気持ちにプラスの効果、逆にマイナスの効果をもたらすのは言うまでもない。
しかし大切なのは、司会者や講師、ファシリテーターだけではない。
参加者の感情も、空気をつくる。
同じ会場、同じファシリテーターによるワークショップであっても
Aグループ
ファシリテーターの話を、目をキラキラさせて、都度うなづくなど反応をしながら聴く参加者。
素直に吸収し、発言の場では、積極的にポジティブな意見を言う。
更に他の参加者にも気配りを忘れない。
Bグループ
ファシリテーターの話を、ほとんど聞いていない参加者。まるで眠っているかのようだ。
リアクションしたかと思えば、否定している様子、虫の居所でも悪いのか、八つ当たりするかのようにネガティブなヤジを飛ばす。
他の参加者への配慮などもちろんない。
Aの参加者が多い場合と、Bが多い場合。
極端な例を出したが
ワークショップの生産性が変わることは明らかだ。
前者であればファシリテーターはノリがますます良くなり、普段は話さないような大切な話しまで「つい話してしまう」なんてことも多い。
これが会議であれば、生産性が高くなり、有意義な時間となるだろう。
つまり会議の「空気」は、参加者の次の「行動」を変えるのだ。
たかが会議と思うなかれ、
「感情」が「空気」をつくり、次の「行動をつくる」
これが良いサイクルになる組織こそ、活性化した、活力ある組織なのだ。
その場に存在する、全員が、その場を、次の行動をつくっている。